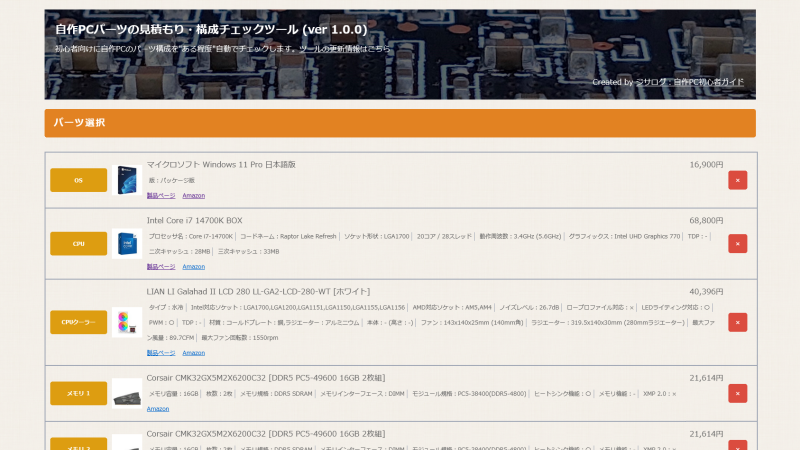電源ユニットには、プラグイン方式によって、ケーブルの管理やメンテナンスのしやすさが変わってきます。
プラグイン対応の電源ユニットは、不要なケーブルを取り除くことで内部のスペースを有効活用できる上に、見た目もスッキリしますし、なんと言っても組み立て時やメンテナンス時の作業効率があがります。
ケーブルの紛失リスクなどのデメリットもありますが、全体的にみるとフルプラグイン、セミプラグインにするメリットの方が大きいですね。
この記事では、それぞれの方式の特徴と、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
電源ユニットのプラグインとは
電源ユニットのプラグインには、次の3つの方式があります。
- フルプラグイン(モジュラー方式)
- セミプラグイン(セミモジュラー方式)
- 直付けタイプ(ノンモジュラー方式)
これらの方式は、自作PCの組み立て時の作業のしやすさやケーブルの取り扱いに違いがあります。
電源ユニットの製品数的には、約7割が直付けタイプの電源ユニットで、最も一般的ですね。
プラグイン方式(フル/セミ)の電源ユニットは、残りの約3割なので少数派にはなりますが、メリットが大きいので人気がありますね。
フルプラグイン(モジュラー方式)

フルプラグイン(モジュラー方式)とは、電源ユニットの全てのケーブルを取り外すことができる電源ユニットです。
この方式の最大の特徴は、使用するケーブルの種類や数を自由に選べる柔軟性にあります。
例えば、PCを組み立てる際に必要なケーブルだけを選んで接続することができ、それにより内部の配線がすっきりと整理され、空気の流れが改善されます。
また、余分なケーブルがないため、ケース内の見た目が美しくなるだけでなく、組み立てやメンテナンスがしやすいという利点があります。
セミプラグイン(セミモジュラー方式)

セミプラグイン(セミモジュラー方式)とは、電源ユニットの主要なケーブルを除き、それ以外のケーブルを取り外すことができる電源ユニットです。
主要なケーブルとは、マザーボード用やCPU用などのパソコンを動かす上で必須のケーブルです。
電源ユニットに直接組み込まれているため、これらのケーブルの紛失や接続ミスを防ぐことができます。
一方で、ストレージやグラフィックボードに接続するケーブルは、使用するものだけを選んで取り付けることができるため、ケース内の配線をすっきりさせることができます。
この点はフルプラグインと同じでですね。
直付けタイプ(ノンモジュラー方式)

直付けタイプ(ノンモジュラー方式)とは、全てのケーブルが本体に固定されている電源ユニットです。
この方式は電源ユニットの中で最も一般的に見られ、電源容量と価格だけに着目すれば、一番コストパフォーマンスに優れていると言えます。
しかし、使用しないケーブルが邪魔になりがちで、PCケース内がごちゃごちゃしてしまうことがあります。
そのため、整理が必要な余分なケーブルをPCケースの隙間に収めるのが面倒というデメリットもあります。
プラグイン対応の電源ユニットのメリット
プラグイン対応の電源ユニットは、PCの組み立てやメンテナンスがスムーズなど多くのメリットがあります。
さらに、直付けタイプと比べても価格が大きく変わらない点も魅力の一つです。
これらのメリットついて、詳しく解説していきましょう。
不要なケーブルの置き場所を考えなくて良い
プラグイン対応の電源ユニットを使用することで、不要なケーブルの置き場所に頭を悩ませる必要がなくなります。
直付けタイプの電源ユニットでは、使用しないケーブルをケース内に押し込んで収納する必要がありましたが、プラグインタイプでは必要なケーブルだけを選んで接続できるため、内部がすっきりと整理されます。
電源ユニットの前に若干のスペースがあり、そこに余ったケーブルを押し込むのですが、ギリギリなことが多いですね。
ケーブルはできるだけ無理な力で曲げない方がいいのですが、そんなことは言ってられない時もあります。
また、電源ユニットの奥行が長かったり、近くにストレージを格納するエリアがあるPCケースだったりすると、スペース的にかなりギリギリなので、使わないケーブルはないに越したことはありませんね。
プラグイン対応であれば、特に電源ユニット周りのスペースが狭い場合には、余分なケーブルを無理に押し込むことなく、スムーズに組み立てができます。
自作PCの組み立てやメンテナンスの作業効率の向上
自作PCの組み立てやメンテナンスを行う際、余計なケーブルがないだけで、作業のしやすさ、組み立てやすさが段違いです。
やはり、このメリットが一番大きく、直付けタイプの電源ユニットで組んだ時はかなり面倒でしたね。
電源ユニットのケーブルは太めなもの、固めなものが多いので、組み立て中に不要なケーブルを手でどけたとしても、戻ってきて邪魔されることが度々ありました…
プラグイン対応の電源ユニットであれば、必要なケーブルのみを接続するため、内部の配線がすっきりと整理され、作業スペースが広がります。
その結果、組み立て時には部品の取り付けがしやすくなり、メンテナンス時には部品の交換や清掃が容易になります。
![]() ケンさん
ケンさん
さらに、将来的なアップグレードを考えた際にも、必要なケーブルを追加するだけで対応できるため、柔軟性に富んだ組み立てが可能となります。
ケースによっては見栄えが良くなる
プラグイン対応の電源ユニットであれば、PCケースの内部の見栄えもよくなりますね。
特に、強化ガラスなどのパソコン内部が見えるデザインのPCケースを使う場合、内部の配線も見えるので、ケーブルの取り回しや整理が重要になります。
基本的には、直付けタイプの電源ユニットでも、強化ガラスからは見えない位置(裏配線側)にケーブルを収納することになるので、直付けタイプでもプラグインでも変わりません。
しかし、PCケースによっては、裏配線ができないものがあったり、見えたりするものもあるので、そういう場合には、プラグイン対応の電源ユニットの方が見栄えは良くなりますね。
メリットのわりに直付けタイプとあまり価格が変わらない
プラグイン対応の電源ユニットは、直付けタイプのものと比べても、あまり価格が変わらないのもメリットですね。
ケーブルが取り外しできる機構がある分、高くなるんじゃないのと思われるかもしれません。
確かに多少は高くはなるのですが数百円~千円程度なので、組み立て・メンテナンスのしやすさ、不要なケーブルを押し込まなくていいことを考えるとかなりお得な気がしています。
配線作業が少なく、メンテナンスや交換が簡単に行えるため、設置や将来的なアップグレードを考えると非常に便利です。
その利便性にもかかわらず、価格は直付けタイプの電源ユニットより少し高い程度なので、プラグイン対応の電源ユニットの方が、全体を見た時のコストパフォーマンスは高いと思います。
そのため、初期投資を抑えつつも、将来のメンテナンスの手間を考慮するユーザーにとって、プラグインタイプの電源ユニットは魅力的な選択肢と言えるでしょう。
プラグイン対応の電源ユニットのデメリット
プラグイン対応の電源ユニットは便利ですが、ケーブルの紛失リスクなどのデメリットもあります。
しかし、メリットを考えると、ないに等しいデメリットなので、あまり考える必要がありません。
ケーブルの紛失リスク
プラグイン対応の電源ユニットを使用する際、ケーブルの紛失リスクは避けられないデメリットの一つです。
必要なケーブルのみを接続して使うため、使用しないケーブルは別途保管する必要があります。
しかし、保管しているケーブルを見失ったり、どこに置いたか忘れたりすることもあるかもしれません。
特に、多くの機器を扱う環境では、ケーブルが散らばりがちで、紛失しやすくなります。
したがって、ケーブルの管理には注意が必要で、適切な保管方法を考えることが重要です。
とは言え、自作PC関連の保管方法として、組み立てた後のPCケースの大きめの段ボールに、他のパーツの箱や余ったネジなどの部品を入れておけばいいので、紛失することは少ないでしょう。
接触抵抗により僅かに供給される電力量が低い
プラグイン対応の電源ユニットでは、ケーブルの差し込み口が各パーツ側だけでなく、電源ユニット側にもあるため接触箇所が増えます。
そのため、接触抵抗が増えるので、理論上は、それが原因で供給される電力量がわずかに低下することがあります。
しかし、実際にはこの影響は非常に小さく、パソコンのパフォーマンスに影響を与えることはないと言えるでしょう。
もしそれで安定した電源供給ができないのであれば、そもそもプラグイン方式の電源ユニットなんて登場しないと思います。
また、電源ユニットは厳しい品質基準に従って作られており、接触抵抗による電力の損失を最小限に抑える設計がされています。
したがって、この点をデメリットとして挙げることはできますが、実際にはほとんど心配する必要はないと言えるでしょう。
まとめ:作業効率、見た目、扱いやすさを考えるなら、セミ・フルプラグインがおすすめ!
電源ユニットのプラグイン方式には、フルプラグイン(モジュラー方式)、セミプラグイン(セミモジュラー方式)、直付けタイプ(ノンモジュラー方式)があります。
プラグイン対応の電源ユニットは、不要なケーブルを気にする必要がなく、自作PCの組み立てやメンテナンスがしやすくなり、PCケースによっては見た目もスッキリします。
また、直付けタイプと比べても価格が大きく変わらないことが多いです。
ケーブルを紛失するリスクなどのデメリットもありますが、組み立てのしやすさなどのメリットを考えれば、プラグイン対応の電源ユニットは十分に選択肢に入ると思います。
作業効率、見た目、扱いやすさを重視する場合は、絶対にセミ・フルプラグインの電源ユニットがおすすめですね。
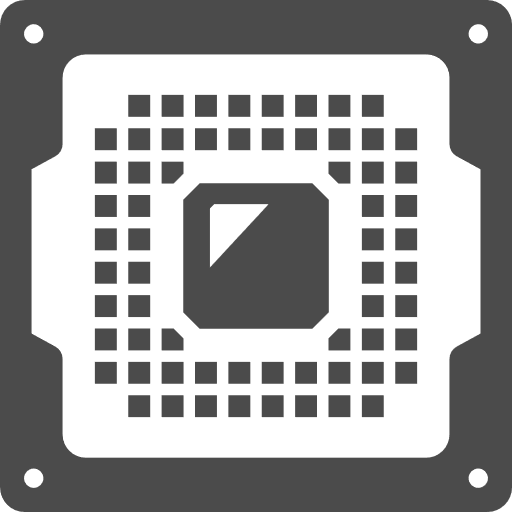 ジサログ:自作PC初心者ガイド
ジサログ:自作PC初心者ガイド